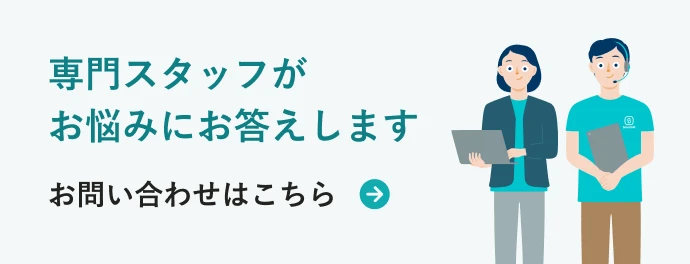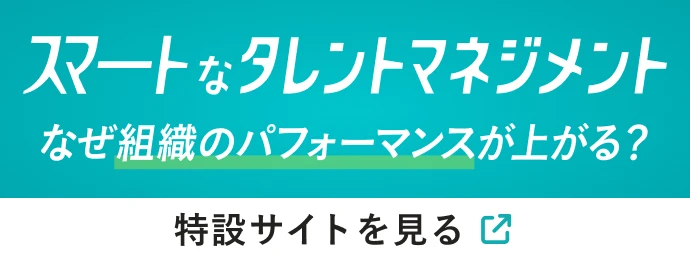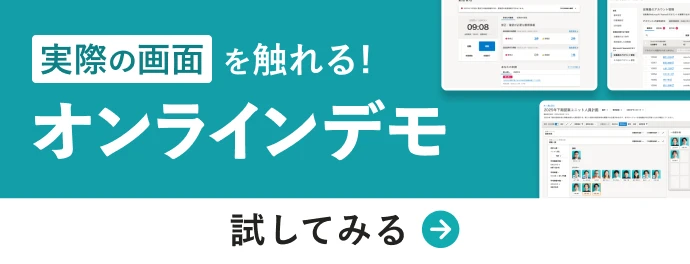人事労務のモデル組織を目指すには、データを蓄積できる「人事マスタ」が必要だった。

| 社名 | 株式会社 SUPER STUDIO |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
課題
- 組織成長に伴って、勤怠・給与など労務管理の強化が必要だった
- 紙やスプレッドシートでの管理では、正しいデータがどこにあるのか分からない状態が発生していた
解決策
- 目視での確認や手作業ではなく、「仕組み」で業務を効率化
- データを蓄積できるシステムを導入し、人事データのマスタを作成
効果
- 煩雑な手続きが全てウェブ上で完結できるようになり、社会保険・入退社手続きにかかる工数が大幅に削減
- 入社手続きにかかる時間は1人あたり1時間程度削減でき、物理的にも心理的にも負荷が減った
- 空いた工数を活かして勤怠管理の強化やテレワーク導入を実施
社会に変革を生み出すべく、挑戦を続けるスタートアップ。企業成長と人員増加に比例して労務管理は重要となり、いかに人力ではなく「仕組み」で従業員に安心を届けるかが勘所となります。
2014年に創業した株式会SUPERSTUDIOは、D2Cのトータルソリューションを提供する企業。同社によるSaaS型のEC基幹システム「EC Force」は250企業以上に導入されるなど、成長を続けています。
本稿では、SUPER STUDIOに1人目の労務担当として入社したコーポレートデザイン室 佐藤 耕平さんと、約70名の頃に入社し、SmartHRを用いて労務の効率化を進めるコーポレートデザイン室 村瀬 寛晃さんに取材を実施。
労務部門立ち上げから今までどのように組織を構築し、課題を解決してきたのかを伺いました。スタートアップ・ベンチャー企業で働く方、必見です。
組織成長に伴って勤怠、給与など労務管理の強化が必要だった
佐藤さんは1人目の労務として入社されたそうですね。
佐藤さん:はい。従業員が50名ほどの時期に入社し、人事労務のオペレーションを回してきました。当時は、給与計算や勤怠管理もガタガタな状態で、「まずは正しく運用を回す」ことにひたすら力を入れていましたね。
ゼロからの立ち上げを担当されたのですね。村瀬さんはどのようなフェーズで入社されたのでしょうか。
村瀬さん:私は従業員数70名ほどの時期、佐藤がマンパワーで運用していたところからステップアップし、労務管理の「質」を高めていくフェーズで入社しました。

SmartHRの導入にはどのような背景があったのでしょうか?
佐藤さん:目視での確認や手作業ではなく、「仕組み」で業務を効率化したいと考えたからですね。それまでは紙やGoogle スプレッドシートでデータを管理していましたが、正しいデータがどこにあるのかわからない状態が度々発生していました。そこで、「マスタ」となるようなデータを蓄積できる人事システムが必要だと考え、SmartHRを導入しました。SmartHRは他の多くの人事系ソフトとAPI連携しており、データを一元管理できる点が特に魅力的でしたね。
ありがとうございます! 他の人事労務ソフトも検討されたのですか?
佐藤さん:していないですね。手続きを効率化することのみに特化したサービスとは異なり、「API連携」によってソフト同士を組み合わせ、人事業務全体を効率化させるというSmartHRのポリシーに魅力を感じ、「人事労務ソフトのマーケットリーダーになる」と考えて導入しました。導入時は、エンタープライズ向けサービスのように細やかな仕様の理解から始める必要もなく、スムーズに導入できましたね。
従業員からの「これはなに?」への対応工数が大幅に削減された
SmartHRを導入してどのような効果が生まれましたか?
村瀬さん:まず、社会保険手続きや入退社手続きにかかる工数が大幅に削減できました。それまでの、フォーマットを作成し、従業員に配布、従業員から集めたデータを手入力する……といった面倒な手続きがすべてSmartHR上で完結できるようになりました。その他のシステムと比較しても格段に使いやすいデザインで、郵送していた書類もウェブ上で対応できるため、テレワーク環境下においても役立っています。
弊社は多い時は月5名ほど新入社員が入社するのですが、入社手続きにかかる時間を1人あたり1時間ほど削減できています。しかも、忙しい月初の1時間×人数分なので、物理的な負荷だけでなく心理的な負荷も減りました。
佐藤さん:それと、従業員からの書類の差し戻しやコミュニケーションコストが大幅に減ったのが非常にありがたかったですね。Google スプレッドシートでの管理だと、「このシートってどう入力すればいいの?」、「この質問ってどういう意味?」などの「これはなに?」という質問への対応が必要でした。1つの質問の対応は5分〜10分程度ですが、積み重なると大きく業務を圧迫します。
SmartHRの場合、質問内容や直感で操作できるおかげで、こういった問い合わせが減り、集中すべき業務に時間を割けるようになりました。従業員が人事関連情報を知りたいと思った時に、労務を介さずにSmartHRを見れば情報をキャッチアップできるのもありがたいですね。

従業員からの差し戻しやコミュニケーションコストをいかに減らすかは労務にとって非常に重要ですよね。SmartHR導入によって空いた工数で新たにできるようになったことはありますか?
村瀬さん:導入前は運用で手一杯だった勤怠管理に、導入後は注力できるようになりました。
工数を大幅に削減できたので、新たな勤怠管理システム「ラクロー」を導入し、より適正な勤怠管理ができる環境を整備できました。また、SmartHRのマスタデータとラクローの勤怠データを組み合わせて、社員ごとの勤怠データ分析も進められているので、勤怠管理の精度も向上しています。
佐藤さん:制度寄りの話だと、最近、新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークへの移行がありましたが、そういった社内の環境整備にも時間を割けていますね。また、オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ」(キャスター社提供)を用いて、労務のルーティンワークを減らすための仕組みづくりなどにも力を入れています。以前と比較して、入社直後の従業員から「スタートアップだけど、けっこう社内の制度や仕組みが整ってますね」と言われる機会も少しずつ増えてきました(笑)。
スタートアップにおける人事労務のモデル組織を目指す
労務組織としての成長が伝わるお話でしたが、「SUPER STUDIOの労務は将来的にこうなっていたい!」といったビジョンがあれば教えてください。
佐藤さん:「スタートアップにおける人事労務のモデル組織」を目指したいと思っています。スタートアップの労務はとにかくやることが多いです。給与計算、勤怠管理など、大きな企業では当たり前に機能している仕組みをゼロからつくる必要があります。
法令遵守した労務管理ができていない企業だとわかってしまうと、会社として求められる他の管理もちゃんとされていないのではないかと、取引に不安を与えてしまうケースもあると思います。
また、従業員のパフォーマンスを最大化するためにも、労務の強固な土台づくりは不可欠です。だからこそ、従業員に「当たり前の安心」を届けられる労務組織を私たちがつくりあげ、他のスタートアップにもナレッジを届けられるようにしたいですね。
村瀬さん:人事労務のモデル組織になるためにも、今以上に労務の「仕組み化」と「効率化」を進める必要があると感じています。ユーザーの自分たちだけでは不可能ですが、SmartHRのマスタデータをベースに他の人事系ソフトとの連携を強めて、ボタンひとつであらゆるデータが連動する世界を実現できたら理想的ですね。

最後に、同じようにスタートアップで労務組織の立ち上げを担当する人たちに向けて、「もし、もう一度労務組織を立ち上げるならどうするか?」をお伺いしてもよろしいでしょうか。
佐藤さん:「ルーティンワークをいかに減らすか」を大事にして労務組織をつくっていきたいですね。労務の仕事はただオペレーションを回すだけだと、従業員からの問い合わせが増えていくだけです。だからこそ、従業員が問い合わせしなくても解決できるような仕組みづくりが重要となります。具体的には、社内の情報インフラ整備やツール導入などに先行投資したいですね。
村瀬さん:オペレーションを回しながらの仕組み化にはパワーがかかりますし、ツールを導入する以上コストはかかりますが、先んじてフローを整備したほうがあとあと楽になると考えています。システムを利用せずに独自の方法で管理をすると、将来的に移行コストが大きくなってしまいます。これからの時代は今まで以上にデジタル化が進み、ツール使用が当たり前になるでしょう。もし自分がゼロから労務組織を立ち上げるなら、ツール同士を連携させつつ、いかに従業員を巻き込んでいくかを意識してやっていきたいですね。
佐藤さん、村瀬さん、ありがとうございました!
※
掲載内容は取材当時のものです。
| 社名 | 株式会社 SUPER STUDIO |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
SmartHR導入に関するご相談、
見積もりのご依頼、
トライアルを受け付けています。