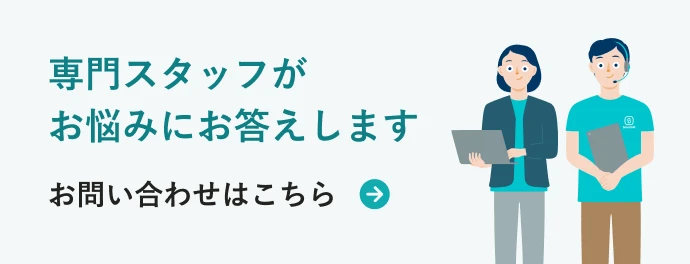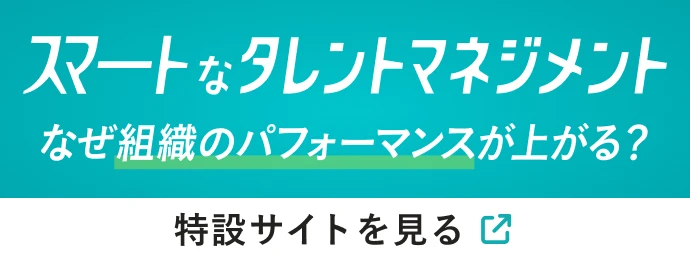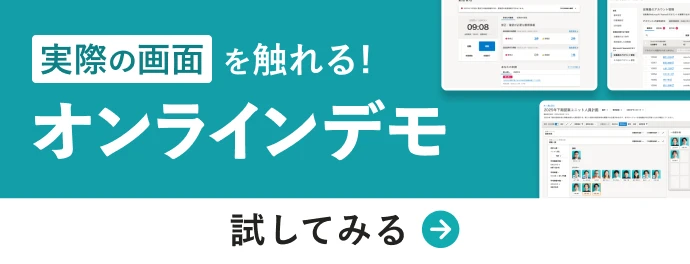「データで語る人事」を目指すファイテンの人事改革。労務効率化を遂げ、人材育成高度化へ


| 社名 | ファイテン株式会社 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
課題
- ベテラン社員のノウハウを確実に次世代に継承する必要があった
- 研修受講履歴などの情報を現場が閲覧できなかった
- 紙ベースの労務手続きによる業務負荷が大きかった
解決策
- 研修情報の一元管理と全社での情報共有を実現
- 研修受講を管理職昇格の要件として設定し、受講の重要性を明確化
- 労務手続きのペーパーレス化による業務効率化を推進
効果
- 管理職や本人から研修情報の閲覧が可能になった
- 研修受講を管理職昇格の要件としたことで、意識が大幅に向上
- 年末調整の処理時間が1か月から2週間に、入社書類準備も1日から1時間程度に効率化
ファイテン株式会社は「すべては健康を支えるために」を企業理念とし、数々のスポーツ・健康・美容商品を世に送り出してきました。オンリーワンの技術開発に注力しており、世界各国で100以上の特許を取得しています。
同社はSmartHRを導入し、人事労務の業務効率化や人材育成の強化に取り組んできました。現在は「データで語る人事」を目指して、タレントマネジメントや従業員データの活用を促進しています。
なぜSmartHRを選び、どのように活用しているのか。また、タレントマネジメント実現を目指す背景とは──。総務・人事部 人事チームの宮本さんにその取り組みについてお話を伺いました。
急成長企業が直面した人事育成の課題。試行錯誤から計画的な育成へ
SmartHR導入以前に抱えていた課題を教えてください。
宮本さん:会社の持続的な成長に向けて、戦略的な人材育成の体制づくりが必要でした。
弊社は創業から41年の歴史のなかで、数々のヒット商品に恵まれ、急成長を遂げてきました。それを支えてきたのは、まさに従業員一人ひとりの努力であり、個人が試行錯誤しながら自己成長していくという企業風土が根付いていました。
これまでの自社の強みを活かしながら、さらなる成長を続けるためには、成長期を支えてきたベテラン社員のノウハウを確実に若手に引き継いでいく必要がありました。そこで2020年ごろに、計画的な人材育成を実現するために専門チームを立ち上げました。
そこではノウハウを確実に引き継ぐという観点から、中間管理職のマネジメントスキル向上に重点を置きました。研修制度の強化から着手しましたが、2つの課題が浮き彫りになりました。

1つめは、研修の優先度が低かったことです。当時は研修受講が任意だったため、現場業務がどうしても優先されてしまい、受講率の低い状態が続いていました。そこで「管理職昇格の要件として特定の研修を義務づける」ことを計画しました。
2つめは、受講履歴などの研修に関する情報を人事部しか閲覧できなかったことです。従来の人事システムは人事しかアクセスできず、情報共有機能もありませんでした。管理職が部下の育成計画を立てる際も、本人が昇格を目指して研修の受講計画を立てる際も、都度人事に問い合わせないと情報がわからない状況でした。くわえて、研修受講情報を人事がもっていること自体を知らない人もいました。
研修管理は人事、現場双方にとって大きな負担となっていましたし、情報が閉じていることが意識醸成の障壁になっていました。また、情報へのアクセスが不平等な状態で研修を昇格要件としてしまうと、昇格機会の有無に格差を生んでしまう懸念もありました。
こうした課題を解決するため、研修管理の効率化と情報アクセスの公平性を実現できる新しい人事システムの導入を検討することにしました。
労務領域ではどのような課題を抱えられていましたか?
宮本さん:労務領域においては業務効率とコストの両面で課題がありました。たとえば入社手続きは紙書類での運用により、書類作成や押印、郵送、保管スペースの確保などにコストや手間がかかっていました。また、年末調整においては給与明細と別システムだったため、データ連携作業などに時間がかかり、大きな業務負荷となっていました。
人事システム選定にあたって意識されていたことはありますか?
宮本さん:これだけDX(デジタル・トランスフォーメーション)の重要性が叫ばれている時代です。人事の領域では、データにもとづく意思決定が重要になると考え、それを見据えてシステムを選ぶべきだと考えていました。
人事課題を経営陣と共有し、理解してもらうためには、データで語ることが必要です。たとえば社員の離職率に課題があるなら「社員がなかなか定着しない」といった感覚的な報告ではなく、データとして離職率の推移を出す方が圧倒的に説得力が増すでしょう。
SmartHR導入の決め手は何でしたか?
SmartHRの社内への導入に際し、社内の反応はいかがでしたか?
宮本さん:導入の稟議では、「従業員データの活用」という新しい取り組みに対して、経営層からは費用対効果について慎重に検証するよう求められました。そこでSmartHRの導入コストと、従来の運用を継続した場合のコスト(人件費、紙資材費、郵送費など)を比較し、さらに従業員データの活用による人材育成強化などの将来像を具体的に示すことで、承認を得られました。
SmartHR導入後は、従業員の利用がスムーズに進みました。マニュアルやサポート体制が充実していたためか、操作に関する問い合わせはほとんどありませんでした。
人事部内でも、「SmartHRスクール」は情報が充実していて誰にでもわかりやすく操作方法が学べるので、特定の人しか使いこなせないといった属人化を防げていると思います。
業務効率化から意識改革まで。SmartHRがもたらした2つの変革
SmartHRを導入して、どのような効果を実感していますか?
宮本さん:まず労務については、ペーパーレスにより業務がかなり効率化されました。たとえば、年末調整では、従来1か月ほどかかっていたものが2週間以内まで短縮できました。また、パート・アルバイトの契約更新における労働条件通知書の合意などは、数百名分の印刷や押印が不要になったことで、準備に丸1日近くかかっていたものが1時間程度で終わるようになりました。
従業員にとっても届出の提出や修正の手間が大きく減ったのではないでしょうか。業務PCをもたないパートタイムの方もスマホアプリでいつでも申請できるので、回収もかなりスムーズになりました。
人材育成の面では、どのような効果を実感していますか?

日常的なキャリア開発から戦略的配置まで。データ駆動型人事への挑戦
今後はどのようなことに取り組んでいきたいですか?
宮本さん:会社の将来を支える人材を育成するために、取り組むべきことはまだまだあります。
まず、現場主導となっている人員配置については、データにもとづいた戦略的な人事配置へと進化させていきたいと考えています。
その土台づくりの第1段階として、SmartHRで人事労務の手続きをペーパーレスにして効率化しました。この段階はほぼ完了したので、現在は第2段階として、従業員サーベイ機能を活用しながら従業員データの収集を進めています。
また、キャリア台帳への情報拡充もさらに進めていきたいです。たとえば、従業員の社内経歴や等級、評価などの情報をSmartHRで一元的に管理できるようにし、全従業員が自身のキャリアを考える際に重要な情報源として活用できる環境を目指しています。SmartHRを年末調整や給与明細の確認だけでなく、従業員が日常的に使うキャリア開発プラットフォームとして確立していきたいと考えています。
今後は、現在の職位や配置の滞留年数などの複合的な分析により、戦略的なジョブローテーションの検討も可能になると思っています。この観点から、「HRアナリティクス」機能の活用も視野に入れています。
最終的には、SmartHRを組織改善のプラットフォームとして活用し、継続的に組織改革を起こし、人材育成を強化していきたいですね。
人事労務のデジタル化は、業務効率化にとどまらず、企業の持続的な成長を支えるデータ資産の構築につながります。ファイテンさまの段階的な取り組みは、まさにその好例ですね。今後も、データにもとづく戦略的な人事施策の実現に向けて、SmartHRとして支援していきます。本日は貴重なお話をありがとうございました。
※
掲載内容は取材当時のものです。

| 社名 | ファイテン株式会社 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
SmartHR導入に関するご相談、
見積もりのご依頼、
トライアルを受け付けています。