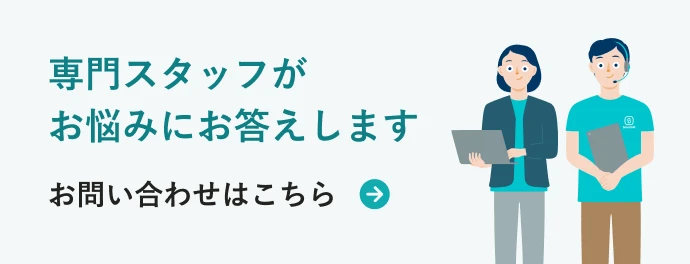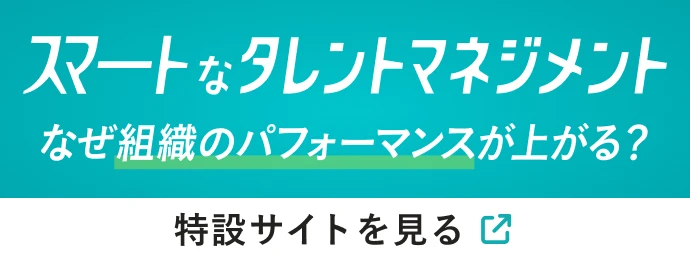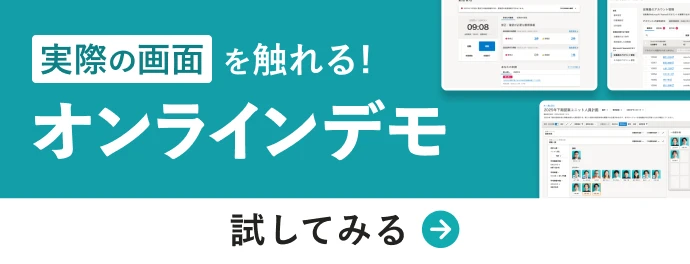散在する人事情報を一元化。評価工数1/3を実現し、タレントマネジメントの土台を築く


| 社名 | 三和化成工業株式会社 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
課題
- 人事情報は紙や表計算ソフトで管理、必要な情報の取り出しが不便
- 緻密に設計した新たな人事評価制度は、アナログでの運用が困難
- 化学メーカー特有の管理すべき資格や講習の情報が多岐にわたる
解決策
- 過去30年分の人事情報を整理し、SmartHRの従業員データベースに集約
- 人事評価機能でシステム化しアナログを脱却、評価業務を効率化
- スキル管理機能で人事部門が資格情報を一元管理
効果
- 人事評価の集計・取りまとめにかかる工数が1/3になった
- 申請をペーパーレス化、拠点間の申請・承認業務が2週間から数十分へ短縮
- 人事情報や資格情報の一元管理が、タレントマネジメント実現に向けた土台に
三和化成工業株式会社は、1947年設立の潤滑油メーカーです。エンジンオイル、工業用潤滑油など各種潤滑油の製造販売を主業としています。基油の販売、石油製品の分析試験のほか、神奈川県の工場に有する日本最大級の危険物倉庫では危険物の保管・配送の事業も手掛けています。
好調な業績を背景に人員が急増していた同社では、新しい人事制度を整備するにあたり、従来のアナログな管理を効率化する必要性に迫られていました。その解決のため2024年にSmartHRを導入。わずか半年という短期間で、人事情報のデータベースの構築から、人事評価制度のシステム化までを実現しました。
スピーディな導入と運用開始の秘訣は、チームワークと目的の共有化にありました。その取り組みの裏側とSmartHR導入の効果について、常務取締役の真田さん、人事総務室長の平山さん、人事総務室 係長の赤平さん、人事総務室の五木さん、太田さんにお話を伺いました。
事業拡大に伴い、アナログな情報管理と複雑な評価制度が課題に
SmartHR導入以前に抱えていた課題を教えてください。
真田さん: 弊社は2年前に、20年ぶりに社長が交代し経営体制が新しくなりました。また近年は事業が好調で、過去10年ほど70〜80名で推移していた従業員数が、ここ1〜2年で100名規模へと一気に増加しました。
中途入社の社員が増えたことをきっかけに、20年近く運用し続けてきた人事評価制度の全体的な再整備を実施、1年前から新しい評価制度をスタートしました。
こうした背景のもと、効率よく人事業務を行なうためには、アナログな管理方法から脱却する必要性に迫られていました。

真田さん: 以前は、従業員の情報を紙や表計算ソフトで管理しており、さらに部門・部署ごとに管理していたため、何か施策を検討する際の情報収集はすべて手作業でした。
従業員が増えたことにより人員配置を検討する頻度も増えましたが、たとえば「年代層や社歴別に社員のリストをつくる」といった基本的な情報収集ですらも、その都度、人事担当者が手作業で情報を拾い集め、取りまとめる必要がありました。
また、新しい人事評価制度では従来よりもきめ細やかな人事評価が可能になった一方で、作業の工数は増大していました。初年度は、従来と同様に表計算ソフトで評価シートを作成、紙に印刷して記入・評価・集計をしていたのですが、あまりにも工数が増えてしまい、いずれ対応が追いつかなくなるという危機感がありました。
人事の業務を効率化し、生産性を上げることを目的とし、その取り組みの一環としてSmartHRの導入を検討しはじめました。
成功の鍵は「チームワーク」と「8割で進める」決断力。半年で実現したスピード導入の裏側
SmartHRの導入はどのように進められたのでしょうか。
平山さん: SmartHRの導入を決めてからまず着手したのが、紙や表計算ソフトでバラバラに管理されていた人事情報の集約でした。
社会保険、口座情報、通勤手当、資格など、「担当者がそれぞれで管理している過去30年分の情報をSmartHRへ集約する」という目標を掲げ、私を含む4名で作業を分担しました。また、評価制度の運用に支障をきたさないよう「2025年5月まで」という期限を定め、従業員データベースの整備と人事評価機能の構築を並行して進めました。

情報の集約はスムーズに進みましたか。
五木さん: 通常業務と平行しながらの作業でしたので、どうしても、業務負荷は一時的に高まりました。
ただ、それぞれの担当者は以前から几帳面に情報を整理してくれていたこともあり、協力をお願いしながら既存の情報を集め、必要な情報を抽出し、SmartHRのインポート形式にフォーマットを整えてインポートするという流れで、1つずつ着実に移行作業を進めていきました。実質的な集約作業は、1か月ほどで完了できたと思います。

御社では従来「情報を整理する」という文化があったのですね。
赤平さん: 普段の業務のなかで「将来、別の手続きなどで必要が生じた際、すぐに情報がわかるよう記録を残しておく」ことを心掛けていました。それが、今回のSmartHRへのデータ集約時に役立ちました。
太田さん: 現職に限らず、過去の担当者の方々が残してくれた資料も活用できました。ただ、記録方法や様式などが統一されていなかったため、関連する情報が複数のファイルに点在する状態も多々ありました。
SmartHRへの集約では、整合性が取れないデータなどから取捨選択して進めることになりました。最終判断する際に役立ったことは、「万が一間違っていても、気付いたときに修正すればいい。8割の完成度でも構わないから前に進めよう」という上長達の方針でした。そのために、作業が停滞することなくスピーディに進められたと思います。
人事評価機能の構築についてはいかがでしょうか。
平山さん: 次期の評価スケジュールに間に合うよう、期限との戦いでした。最大の難関は、評価結果の閲覧権限の設定でした。
弊社では、部門別・職位別に8種類の評価シートを運用しており、評価項目がまったく異なります。まずはそれらをSmartHR上で再現し、どの従業員がどのシートを使うのか、1人ずつ割り当てました。
さらに、評価結果は機密性の高い情報ですので「誰が、どの範囲まで閲覧できるのか」という設定を、チーム全員で指差ししながら一人ひとり確認していきました。
これらの作業は、2〜3か月をかけて丁寧に進めました。
御社はスピーディさの裏で、チームワークよく進めていらっしゃるのが印象的です。
平山さん: メンバーそれぞれが通常業務をもちながらでしたが、導入プロジェクトの会議は必ず全員が時間を取るようにしていました。私たちのいるオフィスは席の間隔も近いので、普段からコミュニケーションを取りやすかったことも、もしかしたら影響しているかもしれません。
真田さん: 導入プロジェクトが成功した一番の要因は、メンバー全員が「自分たちの業務を効率化する」という目的をきちんと理解していたことだと思います。
「今は大変でも、これを乗り越えれば自分たちの業務が楽になる」という意識をみんなが共有できていたことが、チームワークへつながり、限られた期限内での導入、運用開始へとつながったのだと思います。
平山さん: スピーディな導入の背景には、SmartHRのカスタマーサクセスやチャットサポートの方々の存在も大きかったです。
定例の進捗会議で相談に乗っていただいたほか、「この設定方法がわかりません」「この数式がうまく動きません」といったように、わからないことはチャットやメールでどんどん質問させてもらいました。そうした細かな部分まで伴走してもらえたことは、とてもありがたかったです。
評価工数は1/3に、申請業務は2週間→数十分に。“守り”の工数削減と“攻め”のデータ活用基盤を構築
SmartHRを導入して、どのような効果を実感していますか。
真田さん: 効率化の効果をもっとも実感しているのは、人事評価です。
弊社では伝統的にすべての従業員の評価を経営会議で行なっており、最後は社長が一人ひとりに評価コメントを添えています。従来は、1次・2次評価を終えて各部署からメールや紙で提出された評価シートを担当役員である私が集約し、経営会議へ提出するための資料として取りまとめていました。
評価プロセス全体では評価開始から最終決定まで1か月程度、取りまとめ作業だけでも4〜5営業日を要していました。
それがSmartHRによって、少なくとも取りまとめの作業は3分の1程度にまで圧縮できました。ペーパーレス化により物理的な書類のやり取りがなくなり、システム上で評価を進められるようになった効果が大きいです。前の評価者が入力を終えればすぐに次の評価者へデータが回ってきますし、提出が遅れている部署もシステム上で一覧表示されるので、進捗の確認や催促もしやすくなりました。
平山さん: ボタン1つで全データをCSV出力できるので、評価結果の加工・取りまとめは本当に楽になったと感じています。
赤平さん: 細かな部分だと、日々の労務業務ではペーパーレス化により、申請・承認の作業がとても効率化されました。
たとえば、通勤手当の申請などは従来は紙で行なっており、工場だと社内便の本数も限られていて届くのに時間がかかるため、申請から承認まで長いと2週間程度かかっていました。
SmartHRなら、本人が申請を提出すると人事へ直接届きますので、内容に不備がなければ数十分で承認まで完了できます。ペーパーレス化によるスピードアップのみならず、必要な人へ直接届くようになったことで、セキュリティも向上したと感じています。
スキル管理の機能についてはいかがでしょうか。
太田さん: SmartHRの導入によって、これまで各部署でバラバラに管理されていた資格情報を、全社で一元管理できる道筋が見えてきました。
弊社の製造する潤滑油は、消防法が定める危険物にあたるため、業務上で取り扱う場合には乙4(乙種第4類危険物取扱者)の資格が必要です。そのほかにも、取り扱う製品や検査方法などに応じて多種多様な資格や講習受講などが必要となるため、この業界は資格の種類が非常に多いのが特徴です。
法令上で必要な届出や講習受講などは各部署で実施しているため、資格情報も部署単位で管理されており、人事総務室ではそれらのすべてを把握できているわけではありませんでした。
弊社では従来より資格取得の表彰制度がありましたが、SmartHRのスキル管理機能で一元管理できる枠組みができたことで、将来的には保有資格を人事評価へ反映する、といったことにもつなげられるのではないかと思っています。

次なる一手は「組織の可視化」。データにもとづいたタレントマネジメントの実現へ
今後、SmartHRを活用してどのようなことに取り組んでいきたいですか?
真田さん: 1つは「従業員サーベイ」です。従業員数が少ないころは経営層が直接対話する機会もありましたが、組織が大きくなると、どうしても一人ひとりの「顔」が見えづらくなります。
従業員の意識など、経営層からは見えづらくなってしまっている部分を、従業員サーベイによる客観的なデータによって可視化できるのではないかと期待しています。
平山さん: SmartHRへの情報集約を進めていくことで、タレントマネジメントの実現にもつなげられるのではないかと考えています。
将来的には、人事評価や保有資格だけでなく、職務経歴やキャリアサーベイによる意向調査の結果などもSmartHRの「キャリア台帳」へ集約したいと考えています。そうすることで、経営層や人事で人員配置を検討する際の判断材料にでき、従業員にとっても自分の意向に沿ったキャリアが実現しやすい環境がつくれると思います。
真田さん: 将来的には「HRアナリティクス機能」なども活用して、従業員データの利用の範囲を広げていきたいです。
弊社は従業員のほとんどが中途採用であり「このポジションが空いたから、こういうスキルをもつ人を採用したい」という形で採用することが多いため、部署異動や業務内容の変更があまり起こらない、という背景があります。もちろんよい面もあるのですが、一方では、組織が固定化し人材の流動性が下がるという懸念もあります。
従業員データを集約していき、一人ひとりのキャリアが可視化されていれば、配置を検討するうえで大いに参考になります。
また、経営層や人事だけでなく、適切な権限設定をしたうえで各部門でも従業員データを活用できるようになれば、現場からボトムアップによる人員配置の提案が生まれ、さらなるキャリアの活性化へつなげられるのではないかと考えています。
弊社において、SmartHR活用のポテンシャルはまだまだ大きな余地があると思っています。これからも業務効率化や生産性向上のパートナーとして期待しています。
導入から短期間でSmartHRに人事データを集約し、機能活用できた背景や工夫をお伺いでき、大変参考になりました。貴重なお話をありがとうございました!
※
掲載内容は取材当時のものです。

| 社名 | 三和化成工業株式会社 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
SmartHR導入に関するご相談、
見積もりのご依頼、
トライアルを受け付けています。