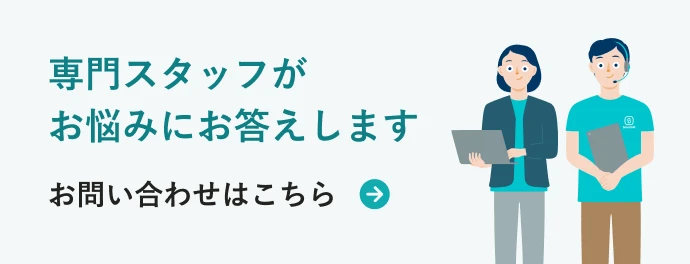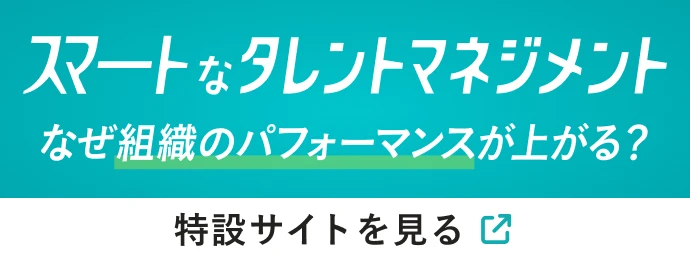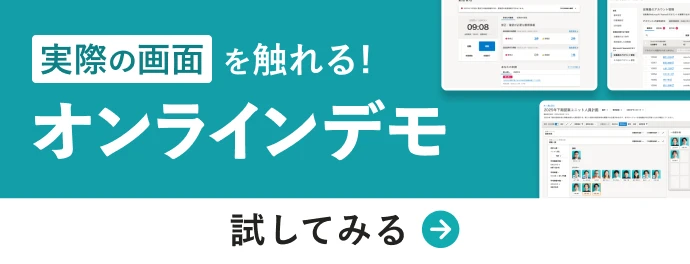“想定外”のサーベイ結果。職員の生の声を起点とした組織改善サイクル
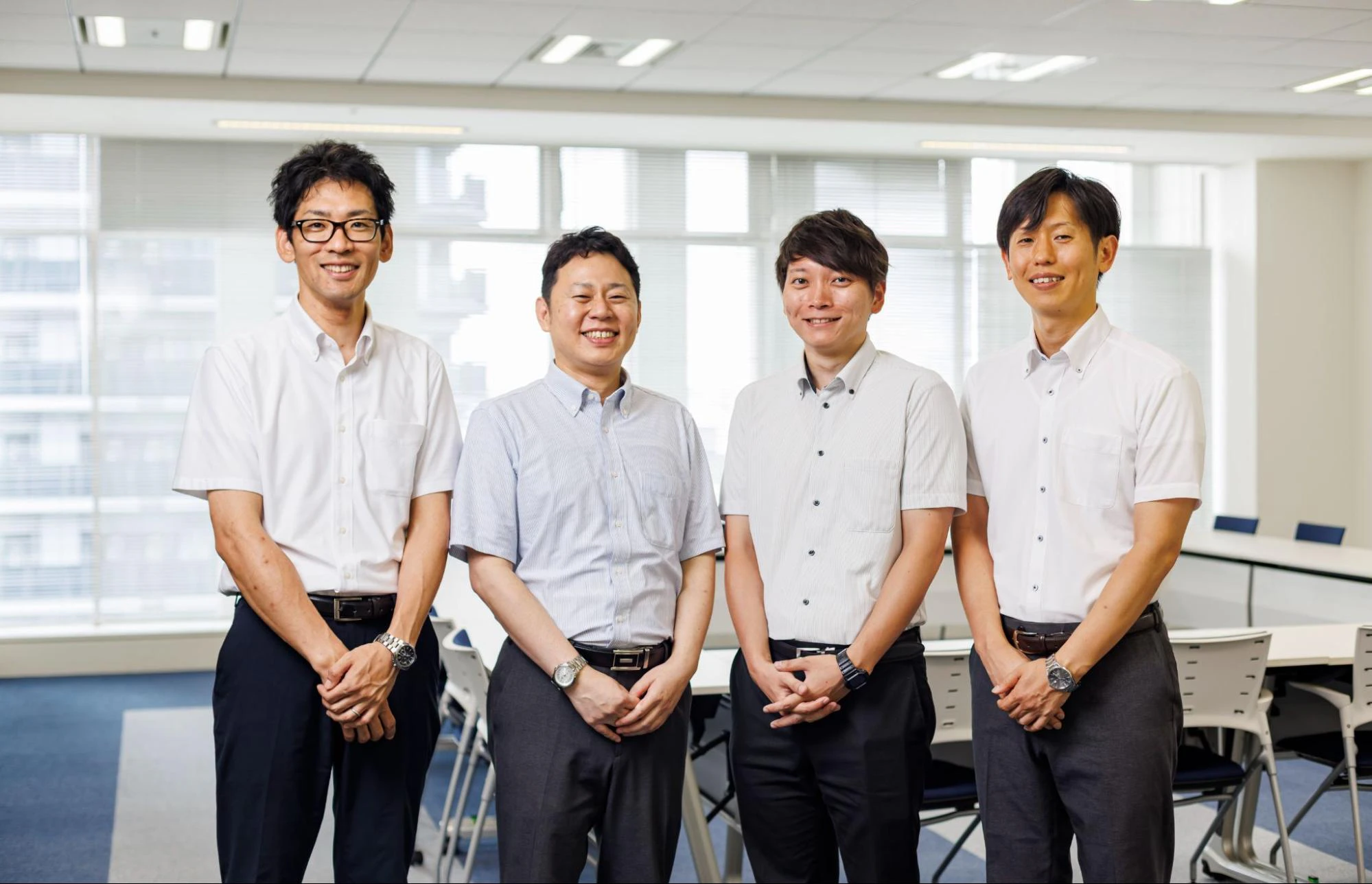

| 社名 | JAあいち経済連 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
課題
- 給与明細や人事考課表が紙のため配付・回収などの運用が煩雑だった
- 旧人事システムはオンプレミス型のため外部への業務委託時の障壁になっていた
- 「人財」のデータベース化を進めてきたが、職員の「生の声」の収集が不足していた
解決策
- SmartHRにより従業員データを一元化
- システムのクラウド化で定型業務を外部委託できる体制を構築
- 職員向けサーベイで「生の声」を集めて課題を特定、施策の企画へつなげた
効果
- SmartHRによる業務効率化とBPOの活用で、最適な人員配置を実現
- 潜在的な課題がサーベイで明らかとなり、より効果的な施策実施が可能に
- キャリア台帳に集約された情報をもとに、質の高い1on1面談が可能に
JAあいち経済連(愛知県経済農業協同組合連合会)は、愛知県内のJA(農業協同組合)を会員とする連合組織で、農業の発展と組合員の生活向上を目的とする団体です。農畜産物の生産から販売までの事業を担い、農家の経営安定や消費者に安全・安心な農産物を提供しています。
同団体ではシステムにより「人財スキルシート」を独自に開発、運用するなど「人」を大切にする風土が根付いています。今回のSmartHRの導入も業務効率化にとどまらず、職員とより向き合うための人事体制を作る目的がありました。
サーベイ実施をゴールとせず、その後の人事施策までどのようにつなげたのか。総務部人事課 課長の林さん、担当課長の亀井さん、総務部人事課の鳥居さん、大澤さんにお話を伺いました。
「同じ作業を5回」非効率業務の改善に着手
SmartHR導入以前に抱えていた課題を教えてください。
亀井さん: 人事が戦略的な業務に集中できるよう、業務を効率化する必要に迫られていました。
当時は人事課に8名の職員がいましたが、紙による給与明細の配付、100を超える部署からの人事考課表の回収と転記など定型業務に多くの時間を割いていました。
このような状態から脱却すべく、業務の一部をBPOサービスへ委託することを検討していましたが、当時はすべての業務システムがオンプレミス型だったため、社外からのアクセスができませんでした。外部委託の前提として社外ともスムーズに連携が取れる環境を整える必要がありました。
また、システム部分にはもう1つ課題があり、当時は業務システム間のデータ連携に多大な工数がかかっていました。勤怠管理や給与計算など業務ごとにシステムが分かれており、それらの間でデータを連携する仕組みがなかったため、データの保守はすべて手作業でした。
たとえば、新入社員のデータを5つのシステムに登録する際には、「同じ更新作業を5回繰り返す」といった非効率な状態で、これも人事部門が定型業務に追われる一因でした。

システムに関して、御社では独自の「人財スキルシート」を開発・運用されていたと伺いました。
林さん: 職員一人ひとりの経歴や保有資格などのデータベースです。年に一度、職員自身で情報を更新し、上司はその内容をもとに面談をしていました。
ただ、役員層が気にしていたのは、定型的な情報だけでは見えてこない職員一人ひとりの“生の声”でした。効果的な人事施策を進めるには、職員がどのような思いで日々の業務に向き合っているのか、その状況や感情を丁寧にすくい上げる必要性を強く感じていたのです。

社外連携のしやすさと「寄り添う」姿勢が導入の決め手に
SmartHRを導入した決め手は何でしたか?
亀井さん: 定型業務の外部委託が最優先事項でしたので、それをどう実現するかという観点で検討を進めました。
最終的な決め手の1つは、委託予定先がすでにSmartHRを利用していたことです。同じシステムを使うことで情報の連携がスムーズになり、外部委託の効果をより大きくできると考えました。
そして、もう1つの決め手は「SmartHRなら自分たちの実現したいことを後押ししてくれる」と感じられたことです。
SmartHRはクラウド型の人事労務システムのなかでも汎用性が高かったこともありますが、それだけではなく、営業担当やカスタマーサクセス担当の方の寄り添ってくれる姿勢が心強いと感じました。
私たちからの「これはできますか?」という問いかけに対して、現状の機能では対応外の内容であっても、「その目的なら、このような方法はいかがですか?」と提案をしてもらえました。検討段階から熱意をもって向き合ってもらえている信頼感こそが、まさに最後の決め手になりました。
導入により最適な人員配置の実現、パート職員との連絡手段を確保
SmartHRを導入して、どのような効果がありましたか?
亀井さん: 数字で示せるものとしては、キャリア意向に沿って2名を営業部門へ配置転換できたことです。
SmartHRの導入とBPOとの組み合わせにより給与計算や勤怠管理などの定型業務が効率化された結果、収益部門の強化につながる人員配置が実現できました。
大澤さん: 定性的な効果は数多くあります。とくに、職員から直接ポジティブな反応を得られたことは、大きな変化だと感じています。
たとえば、文書配付機能を使い給与明細や住民税の通知書を電子化したことで、職員から「便利になった」「これはすごくいいね」という反応がありました。これまでは、人事部門の施策に対してそのような反応は滅多になかったので、やって良かったなと実感しています。


“想定外”の職員の声で気づかされた本当の組織課題
課題に挙げられていた、職員の方々の「生の声」はどのように集まりましたか?
林さん: SmartHRの従業員サーベイでエンゲージメントサーベイを実施し、それが組織の課題を捉え直す大きなきっかけになりました。
サーベイの実施前、私たちは職員のエンゲージメント向上につながるキーファクターをいくつか想定はしていました。しかし、実際のサーベイの結果が示していたのは「自己成長の機会が少ない」という想定外の課題でした。
サーベイを実施しなければこの課題は可視化できず、もしかしたら見当違いの施策をしていたかもしれません。

課題の可視化→分析・議論→施策の実施、SmartHRで一連のサイクルを実現
サーベイ後の施策にスムーズに移行できない企業も多いなか、課題の可視化から次のアクションへ、どのようにつなげられたのでしょうか?
林さん: 最大の要因はトップの強いリーダーシップです。全役員が「サーベイの次の一手が重要であり、ラクではないが覚悟をもって継続的に取り組んでいこう」と明確な意思を示してくれていました。なので、役員と議論して方向性を固め、それを部長会議で協議して理解を得たうえで、決定事項を全部署に展開する流れで進めました。
従業員サーベイの結果は、SmartHR上で簡単に部門ごとの分析ができ、役員や各部門の責任者とも結果を共有し議論に役立てられました。
さきほどの「自己成長の機会が少ない」という課題については、議論を重ねるなかで「コミュニケーションの量は足りていても、個人の内面を深く掘り下げ、将来について一緒に考えるような対話ができていないのでは?」という新たな仮説に至りました。
そこで、次の施策としてSmartHRのプリセットサーベイの1つであるキャリアサーベイを活用し「キャリアプランシート」を作成することにしました。サーベイの結果はキャリア台帳へ自動的に集約されることも、非常に役立ちました。
職員自身にキャリアと向き合ってもらい、その内容をキャリア台帳へ集約する。上司は集約された情報をもとに面談を行ない、必要であれば本人には非公開のメモも残せる。この一連の流れがSmartHR内で実現できたからこそ、サーベイの結果から施策の立ち上げまでスムーズに進められたのだと思います。
サーベイで課題を特定し、キャリアプランシートからキャリア台帳へ、それをもとにした面談へとひとつなぎで機能を活用いただいているのが印象的です。
亀井さん: SmartHRの各機能が、それぞれシームレスに連携しているのがありがたいですね。ここに使い勝手のよさを感じています。

職員の声に寄り添い、働き方改革を次のステージへ
今後はどのようなことに取り組んでいきたいですか?
亀井さん: 今後も定期的にサーベイを実施し、職員のエンゲージメントを継続的に観測しながら、より働きやすい環境づくりを目指していきたいです。将来的には人事労務レポートなどの機能も活用して、SmartHRで得られたデータをさらに分析・活用していきたいと考えています。
林さん:最近では、業務上やむを得ず発生する、休日などの「担当不在時の対応状況」について、サーベイにより可視化しました。職員とお客さまである農家の方々、その間に生じる時間のズレに対して組織としてどう向き合うべきか。今まさに、SmartHRで集まったデータをもとに次の議論を始めたところです。
サーベイを起点に、データにもとづいた対話と施策を繰り返していく。SmartHRは私たちが次のステージへ進むための議論の「きっかけ」を与えてくれる、心強いパートナーだと感じています。
サーベイ結果にもとづいた施策を実施して改善を図るなど、実に効果的にSmartHRをご活用いただけている印象です。この流れをさらに加速させるためにも、引き続きSmartHRをお役立ていただけると幸いです。貴重なお話をありがとうございました!
※
掲載内容は取材当時のものです。

| 社名 | JAあいち経済連 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
SmartHR導入に関するご相談、
見積もりのご依頼、
トライアルを受け付けています。