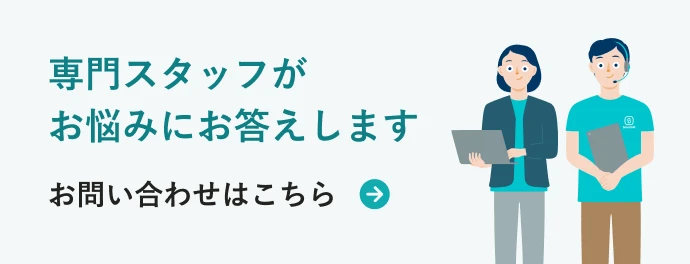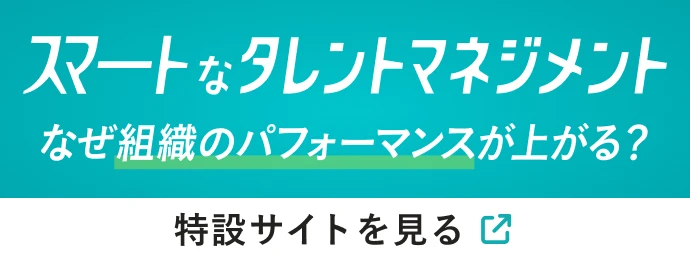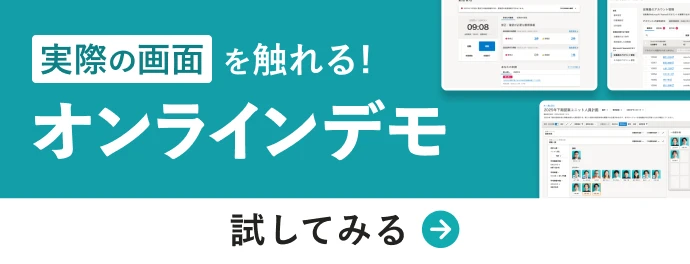2,000名超の総意で導入。日本旅行のデータ活用をフロントシステムとしてのSmartHRが後押し


| 社名 | 株式会社日本旅行 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
課題
- 従業員データの分散により管理が非効率になっていた
- 基幹システムでは未対応の手続きも多く、紙との併用で煩雑だった
- 手続きや申請、押印のために出社が欠かせなかった
解決策
- 基幹システムを補完するフロントシステムとしてSmartHRを導入
- 紙の手続きを減らし従業員情報を一元化
効果
- 手続きや申請、押印のための出社が不要になり、従業員満足度が向上
- 紙の使用量が約6万枚削減、間接部門の作業コストも年間約70時間削減
- 人事・労務担当者の残業時間が削減され、ゆとりが生まれた
2025年で創業120周年を迎える株式会社日本旅行は、国内外に約250の支店ネットワークを展開し、2,422名(2025年1月1日時点)の従業員を抱える歴史ある企業です。旅行を中心としたツーリズム事業のほか、企業や地域の抱える社会課題に挑むソリューション事業、インバウンド事業も展開し、旅行業から顧客と地域のソリューション企業へと進化を遂げました。
こうした幅広い事業展開を支えるのが、バックオフィス業務を含めた徹底的なDX化です。今回は同社で人事・労務領域のDX推進を担当された佐野さんと三宅さんに、SmartHR導入の経緯や導入後の変化、今後のビジョンを伺いました。
「誰もが・すぐに」従業員データを確認できる環境を目指して
SmartHR導入前の課題を教えてください。
佐野さん:SmartHR導入前の課題は、大きく分けて3つありました。
1つめは、従業員データの分散による管理の非効率化です。導入前は、給与や社会保険の情報は人事給与システム、入社日や研修履歴といった従業員情報は別のデータベースや表計算ソフトで管理していました。そのため、経営層から情報の提供を求められた際に、複数のシステムやデータを確認・集約する必要があり、スピーディな対応が難しい状況でした。
2つめは、従業員にとっての手続きの煩雑さです。SmartHR導入前は、住所変更や給与明細の確認、人事評価の閲覧など、確認方法や手段がツールごとにバラバラで、従業員は都度異なる方法で手続きする必要がありました。また、紙ベースの手続きも多く、従業員にとっての負担が大きい状態でした。
3つめは、経営課題としての認識不足です。従業員データの分散が業務効率に悪影響を及ぼしていることは明らかでしたが、具体的な改善効果の数値化が難しく、システム導入による費用対効果を明確に示せませんでした。結果として、この問題が経営課題として社内で十分に認識されていない場面もありました。

全社員アンケートでは「導入希望」の声が大多数
SmartHRの導入経緯を教えてください。
佐野さん:きっかけになったのは、コロナ禍における働き方の変化です。出社制限やリモートワークの増加に伴い、紙ベースの業務に限界を感じるようになりました。さらに、コロナ禍でこれまでの常識が覆されるなか、当社においても経営戦略や事業戦略の見直しが急務となりました。それに伴い、時間や場所を問わず誰もが従業員データをスピーディに確認できるようにしたいという機運が、社内で急速に高まっていきました。
三宅さん :人事・労務システムの導入を社長や経営層に打診するにあたって、全社員アンケートを実施しました。当時、全社員に対してアンケートを取るという文化があまりなかったので、それ自体が大きな取り組みでした。しかし、単純に費用対効果だけを示すよりも、社員の総意を数値化したほうが説得力があると考えました。
その結果、配付から回収まで約2週間という短期間にもかかわらず回収率が高く、回答の内容も「導入してほしい」という肯定的な意見が大多数でした。当時はコロナ禍で出社が制限されていたにもかかわらず、給与明細を受け取るためには出社が必須で、人事評価も上長と対面で行わなければならない状況でした。こうした働き方の変化に伴う困りごとの増加も、システム導入の追い風になったのだと思います。
導入決定の背景には、今後の社会情勢の変化に対応する意図も含まれていたと伺っています。
三宅さん:はい、おっしゃるとおりです。日本が出生者数と労働人口の減少に直面するなか、システムの活用によって従業員を適材適所に配置し、エンゲージメントを向上させて離職を防げるかどうかが、企業の今後を左右すると考えています。当社としてもこうした社会課題と本気で向き合い、中長期的な目線で対策を講じる必要があると考えたことも、導入の大きな要因です。

充実した機能と使いやすさ、親身なサポートが導入の決め手に
SmartHRの選定理由を教えてください。
三宅さん:まず、労務とタレントマネジメント機能の充実です。両方の機能がバランスよく実装されているため、システムの拡張性が高い点が優れていると感じました。また、ベテラン従業員でもスマートフォンやパソコンで操作しやすいシンプルなユーザーインターフェースによる「使いやすさ」も魅力でした。
佐野さん:給与明細・賞与明細の電子化によって、従業員や業務委託先の負担を軽減できそうだという期待感も大きかったです。導入前は給与明細・賞与明細を毎月紙で配付していたのですが、従業員や業務委託先が封入・郵送作業を担当しており、手間がかかっていました。SmartHRで給与明細・賞与明細を電子化することによってこうした作業がなくなり、業務にゆとりが出ることを期待していました。
加えて導入後の伴走体制が充実していたことも、選定の決め手になりました。契約後は基本的に自社での自走となるサービスもあるなか、SmartHRは導入から2年経過後も定期的に打ち合わせを実施いただくなど、担当者が伴走して疑問解決をサポートしてくださっています。システム導入は社内の一大イベントであり、導入後も想定外のトラブルがつきものです。そのため、長期間にわたり親身に付き合ってくださるパートナーの存在が必要不可欠だと考えました。
従業員の定着を促した6つの浸透施策
SmartHR導入において、どのような工夫をされましたか?
三宅さん:1つめは、全社的な浸透戦略です。導入半年前からオンライン説明会やイントラネットでのチラシ配布など、社内での情報発信を繰り返し実施しました。イメージしたのは、映画の予告編です。「202X年X月、SmartHR導入決定!」というように演出込みで打ち出すことで、業務がラクになるんだという期待感を醸成しました。CMのように繰り返し発信することで、従業員の心のなかに浸透させたいという狙いもありました。
発信内容で工夫したのは、専門用語を使わないこと、そして「スマホで給与明細が見られる」というような従業員目線での具体的なメリットを訴求することです。従業員の賛同を得ることからはじめたことで、役員の方々からも理解を得やすい状況をつくりました。
2つめは、既存システムとの連携と情報セキュリティです。従業員個人の金銭に関わる給与情報との連携は、決してミスが許されない部分です。そのため、既存の基幹システムの提供会社とも徹底的に打ち合わせをしました。結果として、給与は従来の基幹システムで計算し、明細表示にはSmartHRを活用するという連携方法を採用し、情報セキュリティに関する承認を得られました。

三宅さん:3つめは、デバイス対応です。全従業員がノートパソコンとスマートフォンいずれかのデバイスを所有・管理する体制を構築し、システムをスムーズに活用できる環境を整えました。
4つめは、SaaS導入におけるマインドチェンジです。SaaSはオンプレミスと異なり、自社の細かいルールに合わせた仕様変更は現実的ではありません。SmartHRを導入したこの機会に、従来の運用をSmartHRの機能に8〜9割方合わせるという意識改革をしました。「最初は大変でも、2〜3か月で慣れる」という楽観的な視点もありました。
5つめは、「先祖返り」させない強い意思です。どれだけ慎重にシステム導入を進めても、「やはり以前のやり方のほうがよかった」という声は必ず出てくるものです。しかし、こうした声に対して「では、今回は特別に以前のやり方でいいです」と言ってしまえば、何も変わりません。ブレずにシステム運用を継続する強い意思を示しつつも、粘り強く丁寧に関係部門と調整を進めました。
6つめは、段階的な機能導入です。全体のスケジュールをスムーズに進められるよう、導入開始にあたっては従業員にとって取りかかりやすい機能・時期を選びました。具体的には、1on1で使用する自社独自の「心情アンケート」から導入しました。当社では毎年1回、従業員が上司との1on1で今後のキャリアについて話し合う機会があります。このタイミングにあわせて導入を開始し、全体の導入計画を立てました。
間接部門の作業コストを年間約70時間削減

SmartHR導入後のシステム構成と役割を教えてください。
佐野さん:SmartHRは、自社開発で20年以上運用している基幹システムを補完するフロントシステムとして活用しています。これまで表計算ソフトで管理されていた給与明細、年末調整、入社時書類、人事評価、自己心情書がSmartHRの機能により実装されました。従業員データがSmartHR上に蓄積されることで、人事・労務業務の効率化や配置、タレントマネジメントに有効活用できるのではないかと考えています。

SmartHRの導入効果を教えてください。
三宅さん:従業員は人事・労務手続きのために出社する必要がなくなり、押印・印刷・上司決裁などの負担が軽減しました。給与明細をスマートフォンから閲覧できることや、年末調整の手書き作業がなくなったことも満足度が高かったです。評価面談のオンライン化により、子育て中の社員などに対して柔軟な働き方をサポートでき、従業員エンゲージメントの向上にもつながっています。
ほかにも、上司は自部署従業員のデータがワンクリックで確認可能になり、状況把握が容易になりました。人事・労務担当者は確認作業や発送業務がなくなり、ゆとりをもって業務にあたれるようになりました。残業時間も削減できています。

佐野さん:事業部間の連携がスムーズになったことが、人事評価の工数削減につながっています。紙の使用量は2年間で約6万枚削減、給与明細配送、人事評価原本印刷といった間接部門の作業コストは年間約70時間の削減を実現できました。

企業価値向上に向けてグループでのSmartHR活用を推進
最後に、今後の展望を教えてください。
佐野さん:私たちの目標は、顧客と地域のソリューション企業グループとして企業価値向上に貢献することです。そのためには従業員一人ひとりのキャリア希望に寄り添う配置や評価を実現し、従業員エンゲージメントをさらに向上させていかなければなりません。SmartHRに蓄積される従業員データを活用し、配置シミュレーションなどの機能で人事情報を可視化し、有効に活用することで、それが可能になると考えています。
今後はグループ全体へとSmartHR活用の輪を広げ、人事戦略が事業戦略や経営戦略に貢献し、その効果が従業員に還元されるというプラスの循環を生み出していきたいですね。
三宅さん:SmartHRを導入するのがゴールではなく、導入後にどう活用して目標達成につなげるかが重要であるとの思いでこれまで導入を推進してきました。引き続き初心を忘れずに、グループ全体でSmartHRの活用を推進していきたいと思います。
創業120周年という歴史ある企業で、未来を見据えたDX推進に挑戦されているエピソードは、多くの企業にとって大きなヒントになると感じました。今後、グループ全体での活用が進み、さらなる企業価値向上に向けてSmartHRをお役立ていただけると幸いです。貴重なお話をありがとうございました!
※SmartHRでは多様な業種・業界を対象とした事例紹介セミナーを定期的に開催しております。本記事は2025年8月7日の講演内容をもとに制作しています。
関連:歴史ある企業はどのようにDXを実現するのか。事業成長の「次の一手」に向けた人事労務部門の取り組み(株式会社日本旅行)
※
掲載内容は取材当時のものです。

| 社名 | 株式会社日本旅行 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
SmartHR導入に関するご相談、
見積もりのご依頼、
トライアルを受け付けています。