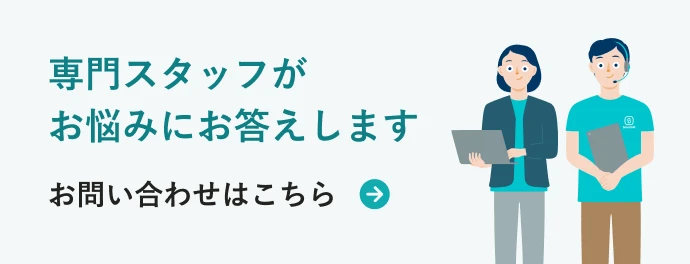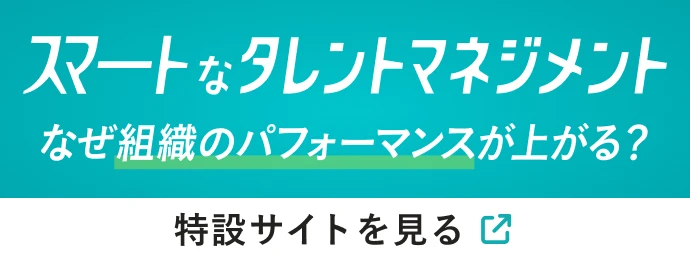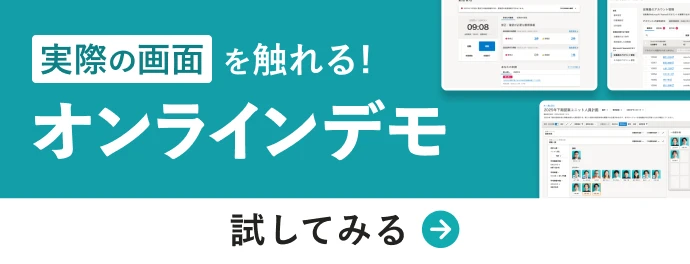年間42,500時間の業務削減。従業員5万人超“世代を超えた”労務ペーパーレス化


| 社名 | 日清医療食品株式会社 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
課題
- 全国約5,000拠点からの紙による申請で郵送・確認に時間がかかる
- 申請書類の紛失が頻発、従業員・管理者の心理的負担が大きい
- 年末調整や給与明細の発行も紙主体で、運用が煩雑
解決策
- SmartHRによる労務手続きのペーパーレス化を推進
- 帳票の電子化・業務フローの統一を支店と連携して実施
- スマホをもたない人向けに店舗の勤怠用タブレットを申請端末として活用
効果
- 年間約17万件の紙申請を電子化、約42,500時間の業務時間を削減
- 申請のタイムラグや紛失リスクが解消、保管スペースも縮小
- 申請状況が可視化され、従業員・管理者双方の心理的負担が軽減
病院・福祉施設向けの給食受託業務で国内トップシェアを誇り、全国5,445拠点でサービスを提供する日清医療食品株式会社。従業員は約5万4,000人うち4割が60歳以上と、幅広い年齢層の人材が活躍しています。
同社では全社的な業務改革プロジェクトの一環としてSmartHRを導入。紙ベースの労務手続きによる業務負荷の解決に向けて、現場の状況に寄り添いながら改善を重ねてきました。
今回は導入を担当された総務本部 人事部 労務課 課長の安田さん、係長の吉川さんに導入の背景や成果、現場での工夫を伺いました。
紙ベース運用による時間ロスと紛失リスク、「ちゃんと届いたか」の不安
労務手続きについて抱えていた課題を教えてください。
安田さん:従業員の入社手続きや身上変更など、申請書類をすべて紙でやり取りしており、フローが非常に複雑でした。
まず、従業員が紙の書類を記入し、事業所のチーフに提出します。そこから営業所や支店へ郵送、あるいは事業所を巡回するスーパーバイザーが車で回収していました。
支店に届いた後も、複数の部署や役職者による承認・捺印を経て、最終的に総務部に届きます。総務部が手続きを開始するまでに、非常に時間がかかっていました。支店到着後手続き着手に1週間以上要することも珍しくありませんでした。
時間的な負担以外に、どのような課題がありましたか?
安田さん:多くのステップを踏むなかで、大切な書類が他の書類などと紛れてしまうなど紛失のリスクもありました。
また、紙書類のステータスが誰にもわからない、という問題もありました。申請した従業員は「ちゃんと届いただろうか」と不安になりますし、問い合わせを受けた支店の総務担当者も「今、支店長のところか、それともまだ担当者の手元か…」と探すのに苦労する。
この「どこにあるかわからない」という状況が、双方にとって大きな心理的ストレスになっていました。
全社横断プロジェクトでSmartHRを選定。「将来への期待感」が決め手に
課題に対し、どのように解決策を検討されたのでしょうか。
安田さん:2018年に業務効率と従業員満足度向上を目的とした全社横断プロジェクトが発足しました。その一環として、個人申請業務の標準化・統一化、電子化・ペーパーレス化を進める企画が立ち上がったのです。
そのなかで複数の労務申請系システムを比較検討し、SmartHRを選びました。シェアの高さに加えて、機能の拡張性や今後のプロダクトの進化に期待をもてた点が決め手になりました。

貴社ほどの規模の組織ですと、新しいシステムを導入する際、稟議を通す際は大変だったのではないでしょうか。
安田さん: 稟議にあたっては、導入後のサポート体制を強化するために、本社の人事部に専門の担当者を1名増員することも含めて費用をすべて織り込み、上申しました。
現場の問い合わせが増えることを見越し、支店の担当者が不安なく運用を開始できるよう体制を整えたのです。
プロジェクトが業務効率と従業員の満足度向上という全社的な目的を掲げていたため、経営層含め社内の認識も揃っており、承認を得やすかった面もありました。
5万人の従業員への浸透。現場を巻き込み「本支店一体感」を醸成
導入後、どのような工夫をされましたか?
安田さん:導入後にまず課題となったのが「5万人の従業員、5,000か所の拠点へ、どう浸透させるか?」という点です。
具体的には次の4つの取り組みを重点的に進めました。
(1)現場を巻き込み、「本支店一体感」を醸成
本社だけでなく支店の総務部員にもプロジェクトメンバーに加わってもらい、紙帳票の電子化や業務フローの統一化をともに進めました。
本社主導ではなく支店の総務実務担当者とともに動いたことで、納得感や一体感が生まれたと思います。
(2)スモールスタートで運用課題を事前に洗い出し
まずは一部の支店・地域でトライアル導入を実施し、細かな運用課題を先に把握しました。事前に対応策を講じることで、全国展開もスムーズに進められました。
(3)本社に専門部員を置いたサポート体制の整備
導入後は支店からの問い合わせの増加が予想されたため、本社の人事部に専門部員を増員し、対応体制を強化しました。
支店総務部員の不安を最小限に抑えることで、各現場が安心して運用を始められるようにしました。
(4)従業員メリットの丁寧な伝達・訴求
SmartHRの導入によって「支店総務だけでなく、現場で働く従業員にもメリットがある」という点を丁寧に伝えるようにしました。
具体的な方法として、本社主導で事業所チーフ向け・スーパーバイザー向け・支店総務部向けといった階層別のオンライン説明会を実施しました。説明会動画は当社の動画プラットフォームへ一定期間保存し、当日出席出来なかった方も視聴できるようにしました。
業務効率化が自分たちの働きやすさにもつながるという理解を広げた結果、全社的な納得感にもつながったと感じています。
既存のタブレット活用でスマホを持たない従業員にも配慮
スマートフォンをお持ちでない方の導入も工夫されたと伺いました。
安田さん:SmartHRを導入した2020年当時、とくに高齢の従業員のなかにはスマートフォンを持っていない人が10%から15%ほどいました。そうした方々が取り残されてしまう状況は避けなければなりません。
そこで活用したのが、SmartHR導入より少し前に導入していた勤怠打刻用のタブレットです。各事業所に設置されているこのタブレットにSmartHRを設定し、私用のスマートフォンがない方でも、事業所で各種申請ができる体制を整えました。すでに勤怠打刻で使い慣れている端末だったため、従業員の方々も比較的スムーズに受け入れてくれたと感じています。
共有端末ならではの運用ルールも必要だったかと思います。
安田さん:「SmartHRログインしたら必ずログアウトする」というルールを設けました。また導入当初はログインのセッション時間を短めに設定していました。わかりやすいルールの徹底がスムーズな運用につながったと感じます。
そのほか、導入において工夫された点はありますか?
吉川さん:導入を進めるなかで、従業員から「操作がわからない」「入社手続きのシステム自体を見直したほうがよいのではないか」という声が社内で上がったことがありました。
その際には、SmartHRのカスタマーサクセスの方に相談しながらマニュアルを作成したり、システム改修をしたりと対応いただきました。いつも素早く返答いただき助かっています。

年間42,500時間削減。申請の「見える化」で心理的負担も軽減
SmartHRの活用範囲を教えてください。
安田さん:主に4つの業務領域で活用しています。
- 雇入時提出書類の申請(住所、通勤手段、振込先口座、扶養親族、資格など)や身上変更時書類の申請
- 給与明細や源泉徴収票、 労働条件通知書(雇入時、契約更新時)、会社からの各種お知らせなどの文書配付
- 社会保険得喪および各種届出、雇用保険得喪および各種届出
- 年末調整書類の配付、年末調整書類の回収、チェック
年末調整については、SmartHR導入時から徐々に対象の支店を増やしてきました。現在ではすべての従業員が年末調整機能を利用しています。
導入によって労務手続きはどう変わりましたか?
安田さん:従業員が自身の各自のスマートフォンやパソコン、事業所のタブレットから各種申請を実施すると、すぐに支店の総務担当者が内容を確認できるようになりました。
紙の書類の作成や郵送にかかっていたコストや時間が大幅に削減されています。以前は悩みの種だった書類の紛失リスクも、ペーパーレス化によって心配がなくなりました。
差し戻しも大きく改善しました。紙のときは、従業員に電話で理由を伝え、修正点を記入して再提出してもらう必要がありましたが、SmartHRでは差し戻しと同時にリアルタイムで通知が届き、コメントも添えられるため、やり取りの手間がほとんどなくなりました。
何より申請者も管理者も「今、書類はどこにあるのか」という進捗状況をリアルタイムで確認できるようになったインパクトは大きかったです。双方のストレスが解消され、業務に集中できる環境が整いました。
定量的な効果についても伺えますか?
安田さん: 定量面では、これまで紙で運用していた社内書類26帳票をSmartHRに移行したことで、年間約17万件の申請が電子化されました。1件あたりのチェック時間を約15分と仮定すると、年間で42,500時間もの作業時間を削減できた計算になります。
また、社会保険や雇用保険に関する行政手続きも電子申請に切り替えたことで、手続きが大幅に迅速化されました。紙の保管スペースも削減できました。
吉川さん:管理者側から従業員へのお知らせも、文書配付機能を活用することで効率化されました。
例えば、法改正に伴う育児・介護休業に関するお知らせなど、以前は紙で印刷して誰かが手渡しする必要があったものを、SmartHRで全従業員に直接、かつ確実に届けられています。これはペーパーレス化の大きなメリットだと感じています。

データ連携強化と「誰一人取り残さない」DXを追求
最後に、SmartHRの活用における今後の展望を教えてください。
安田さん: 1つ目は既存の人事給与システムとのデータ連携です。現在はSmartHRで申請された情報を手作業で人事給与システムに入力している部分があるため、ここを自動連携させて支店担当者の作業負担を削減したいと考えています。
2つ目が、マイナンバーの収集・管理のSmartHRへの移行です。現在は別の仕組みで管理していますが、SmartHRに一本化することで必要な行政手続きのさらなるスピードアップを図りたいです。
最後は、誰にでも優しい操作性の実現です。弊社は幅広い年齢層の従業員がいますので、動画マニュアルの充実など社内での工夫を続けるとともに、SmartHRのさらなる進化にも期待しています。誰一人取り残すことなく、システムの恩恵を受けられる状態を目指していきたいです。
ありがとうございます。 今後も「誰一人取り残さない」DXのパートナーとして、SmartHRが伴走させていただけると嬉しいです。
※ SmartHRでは多様な業種・業界を対象とした事例紹介セミナーを定期的に開催しております。本記事は2025年5月28日の講演内容をもとに制作しています。
※
掲載内容は取材当時のものです。

| 社名 | 日清医療食品株式会社 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
SmartHR導入に関するご相談、
見積もりのご依頼、
トライアルを受け付けています。