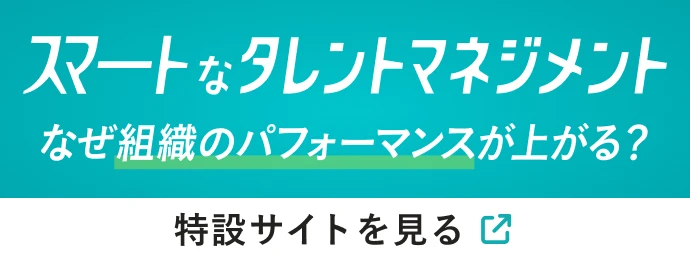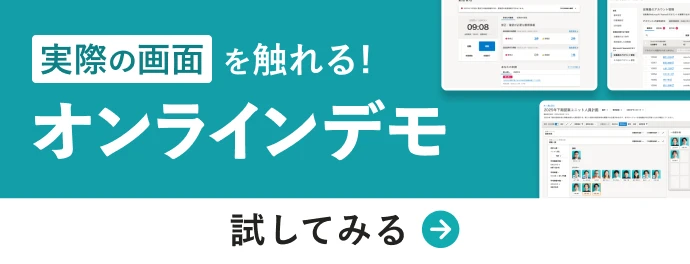医療・介護の現場でも連絡・手続きを滞留させない。「メッセージ」機能活用で伝言ゲームをなくす


| 社名 | 医療法人社団 英世会 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
課題
- 現場はシフト勤務や対人業務が多く、情報伝達が常に上長経由の「伝言ゲーム」に
- 人の命・健康に関わる業務が優先。人事・労務の手続きが遅れ、職員・上長・本部に大きな負担
- 夜勤など多様なシフト制、かつ多忙な職員は本部からの依頼をタイムリーに受け取れない
解決策
- SmartHRの「メッセージ」機能を導入し、職員へ直接連絡が取れる体制を構築
- ファイル添付の機能を活用し、これまで郵送や手渡しだった書類のやり取りをオンライン化
効果
- 伝言ゲームがなくなりコミュニケーションが迅速に。職員・上長・本部の三者の負担が軽減
- 職員はスマートフォンアプリから自身の都合のよいタイミングで確認・返信できる
- 書類の不備確認や提出依頼がスムーズになり、郵送コストや手間が大幅に削減された
医療法人社団 英世会は、東京都日野市を中心にクリニック、介護老人保健施設、保育園など、多岐にわたる医療・介護サービスを地域に提供しています。
医療・介護の現場では、日勤・夜勤などのシフト制勤務や、人命に関わる対人業務であるがゆえに、業務時間中に職員へ直接連絡を取るのが難しい場合があります。 約690名の職員が在籍する同法人でも、人事部門と職員とのやり取りが常に「上長を介した伝言ゲーム」状態となっており、業務負荷や情報伝達の正確性に課題を抱えていました。
この課題を解決すべく導入されたのが、SmartHRの「メッセージ」機能です。導入の経緯や具体的な活用法について、法人本部 総務室長の田畑さん、同・経理室長の上田さん、同・財務管理室 兼 経営企画室の近(こん)さんにお話を伺いました。
伝言ゲーム、タイムラグ、煩雑な紙業務… 医療・介護の現場特有のコミュニケーション課題
職員の皆さまとのコミュニケーションにどのような課題がありましたか?
上田さん:本部から職員へ連絡を取る場合、基本的にはすべて各施設の事務長を介していたところに大きな課題がありました。
職員は早番、日勤、遅番、夜勤といったシフト制で働いており、勤務時間や休日がまちまちです。業務時間中は施設内を動き回っているので、PCなどの連絡ツールを確認できるタイミングが少なく、また、業務用のPHSをもち歩いている職員も限られています。
そのため、職員へ個別に連絡する方法は基本的に口頭か内線しかなく、本部から各施設の事務長にお願いして、連絡を取ってもらう必要がありました。
しかし、本部や事務長の勤務時間は平日の日中なので、対象が夜勤明けの職員である場合などは、連絡が取れるのは早くても数日後、ということが往々にしてありました。

近さん:職員は常に現場を忙しく動き回っていますので、コミュニケーションのハブとなる事務長も、誰がどこにいるのか把握しているわけではありません。
そのため、本部から依頼を受けた事務長が、まずは内線でステーションに電話をかけ、本人が不在であれば電話口の職員に探しに行ってもらう必要がありました。
本人を見つけても、人の命や健康に関わる仕事ですから、処置中であればもちろん話はできません。とにかくタイムリーな連絡が難しかったです。

上田さん:また、個人情報に関わるやり取りなどは、周囲に漏れ伝わらないよう気を付けなければならないので、とくに時間を要しました。手が空いたら事務長室を訪ねるよう声をかけるか、人事・労務関連の必要書類を封筒に入れて手渡し後に回収するといった方法しかありませんでした。
ただ、「手が空いたら」と言っても、忙しい医療・介護の現場では「手が空く時間」などそうそうないので、忘れてそのまま退勤してしまうケースもありました。
そのような状況下、事務長側も「この時間帯は忙しいから職員に迷惑かもしれない」と遠慮して本部からの連絡がますます滞っていました。
ご苦労が多かったのは、具体的にどのようなやり取りでしょうか。
田畑さん:たとえば、入社手続きの書類に関する連絡です。
従来は、入社時に紙の書類を本人から事務長へ提出し、事務長経由で本部へ郵送していました。書類に不備があった場合、それが発覚するのは本部が受け取ったタイミングです。修正するにはまた事務長を介して本人に連絡し、郵送で書類を返送、再度提出してもらう必要があり、非常に時間がかかっていました。
また、産休・育休中の職員との連絡にも課題がありました。年間で7〜8名ほどになりますが、育児休業給付金の決定通知など、書類を各職員の自宅宛てに個別で郵送する必要があり、手間もコストもかかっていました。
.jpg?fm=webp&w=6000&h=4004)
上田さん:年末調整も以前は紙ベースで実施しており、申告書の未提出者への催促や書類不備の差し戻しもすべて事務長経由でした。そのため、わずかな確認だけでも日数がかかってしまいます。
とくに期限が定められた人事・労務の手続きを完了させるのはまさに時間との勝負で、本部はもちろん、職員に連絡する事務長や業務のかたわらで対応する職員本人も、すべてにとって大きな負担となっていました。

「メッセージ」機能を追加でご契約いただいた決め手を教えてください。
近さん:事務長を経由するコミュニケーションの非効率さは、経営陣も法人全体の課題として認識していました。
また、人材不足が叫ばれる昨今においては、会議などで「生産性を高めていかなければ将来的に立ち行かなくなる」という危機感が常日頃から共有されていました。
SmartHRの「メッセージ」機能なら現場のコミュニケーションの課題が解決でき、業務全体の効率性も上がるのではないかという期待感から、導入へと至りました。

時間と場所を選ばない連絡体制で「三方よし」のコミュニケーション改革を実現
「メッセージ」機能を導入され、どのような効果を実感されていますか?
上田さん:まず、本部と職員が直接やり取りできるようになったことで、事務長の負荷は大きく軽減されたと思います。「メッセージ」機能の導入前は、本部からの伝言対応や、シフトの関係で職員本人に伝えられなかった事項を数日後に伝えるなど、大きな心理的負担があったと思います。現在は、事務長を介する必要がなくなったため、こうした課題を解消できています。
本部としても、職員にメッセージを届ける際は、「業務が一段落したタイミングで確認してほしい」と考えています。そのため、当該職員のシフトや業務状況を気にしすぎず連絡ができ、本当に助かっています。
田畑さん:職員にとっても、自分の都合のよい時間に回答できるようになったことは大きいと思います。実際に、夜勤の職員が深夜2時ごろの休憩中に、「メッセージ」機能で回答を送信してくれていました。
従来は夜勤の職員と連絡が取れるまでに数日かかることもありましたが、今では私たちの退勤前にメッセージを送っておくと、翌朝には夜勤の職員から回答が来ている、というケースも増え、タイムラグが大きく減少しました。
ご苦労されていた「入社手続き」についてはいかがでしょうか。
田畑さん:紙ベースだった入社手続きはペーパーレスになり、以前は事務長を介して何日もかかっていた書類の回収スピードが大幅に短縮されました。
もし提出された情報や添付書類に不備があっても、「メッセージ」機能で本人と直接やり取りできるため、事務長の手をわずらわせず効率的です。
また、細かな点を職員に確認したい場合など、連絡にかかる心理的なハードルが大きく下がりました。
たとえば、以前は源泉徴収票の申告区分を「乙欄」に記入していた方がおり、これが「事実」なのか、単に記入を間違えただけなのか判断がつかないケースがありました。 「メッセージ」機能を使えば、このような間違えられないから念のため確認しておきたいときにも本人と手軽にやり取りができ、非常に助かります。
また、「メッセージ」機能にはファイルが添付できるのが便利ですね。PCのなかをあちこち探し回らなくても、SmartHR上から必要な書類をすばやく選んで送れるため、個人的にとても気に入っています。
たとえば、産休・育休者へ書類を送る際にも、「メッセージ」機能でPDFファイルを添付して送れるようになり、郵送の手間がなくなりました。「メッセージ」機能では「既読」になったかどうかが確認できるので、きちんと見てもらえている安心感もあります。
職員側も、スマートフォンアプリから書類が提出できるため、小さなお子さんを抱えながら郵便局へ差し出しに行くといった手間がなくなり、楽になっているようです。
ほかにも、扶養者(異動)届で配偶者の給与明細が添付されていなかったケースでは、本人へ不備を伝えたところ「今日帰宅したら送ります」と返事があり、スマートフォンで撮った写真をすぐに提出してくれました。おかげで、滞りなく手続きを進められました。
上田さん:職員は、時間や場所を気にせず、自分のタイミングで本部からの連絡を確認し返信できる。事務長は、これまで負担となっていた伝言業務から解放される。そして、私たち本部は、迅速かつ正確なやり取りができ業務をスムーズに進められる。
職員・事務長・本部の全員にとって、「メッセージ」機能は大きなメリットがあったと感じています。
コミュニケーション改革のその先へ。さらなる生産性の向上を目指して
今後はSmartHRをどのように活用されたいとお考えですか?
田畑さん:SmartHRには便利な機能がたくさんあるので、さらに活用していきたいです。
「メッセージ」機能以外で活用しはじめたものとしては「AI履歴書読み取り機能」ですね。これが非常に便利です。
たとえばメールアドレスは、手書きで崩れたような文字列でもかなり正確に読み取ってくれます。1文字ずつ神経を使って入力していたものが、間違いがないかざっと確認するだけで済むようになり、応募者さまへの連絡の際にメールが不達になることもなくなりました。
また、履歴書から読み取ったデータをもとに、そのまま雇用契約書の作成、給与ソフトへのデータ連携までスムーズに行なえるようになり、手入力していた作業を効率化できました。
今後は、職員におけるスマホアプリの利用なども、一層促進していけたらと思っています。
近さん: SmartHRを導入してからちょうど1年になります。最初はどのようなものか分からず、業務が効率化できると説明を聞いても、まるで夢のような話だと感じていました。 それが、今では「メッセージ」機能をはじめ、AI履歴書読み取り機能や、「文書配付」機能などへ活用の幅が広がっており、導入して本当に良かったと感じています。
今後、組織として生産性をますます高めていかねばならないなかで、SmartHRの活用もさらに進めていければと考えています。

本部の皆さまだけでなく、医療現場で活躍する職員の皆さまに導入メリットがあったこと、嬉しく思います!引き続きSmartHRがご支援できるよう改善を進めてまいります。貴重なお話をありがとうございました!
※
掲載内容は取材当時のものです。

| 社名 | 医療法人社団 英世会 |
|---|---|
業種 | |
| 従業員数 | |
| 課題 | |
| 都道府県 | |
| 機能・サービス | |
機能の詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
SmartHR導入に関するご相談、
見積もりのご依頼、
トライアルを受け付けています。



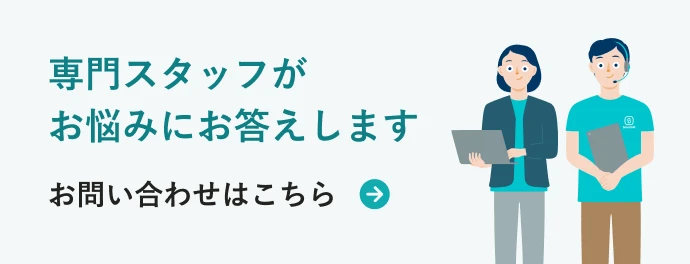


.jpg?fm=webp&w=700&h=408.33333333333337)

.jpg?fm=webp&w=700&h=408.33333333333337)